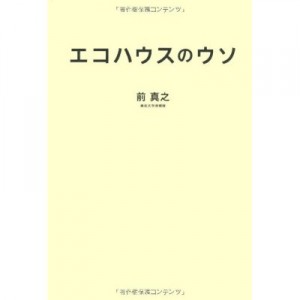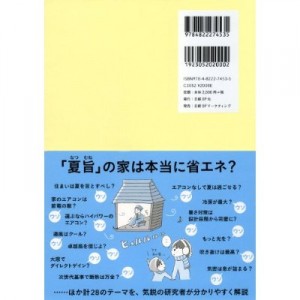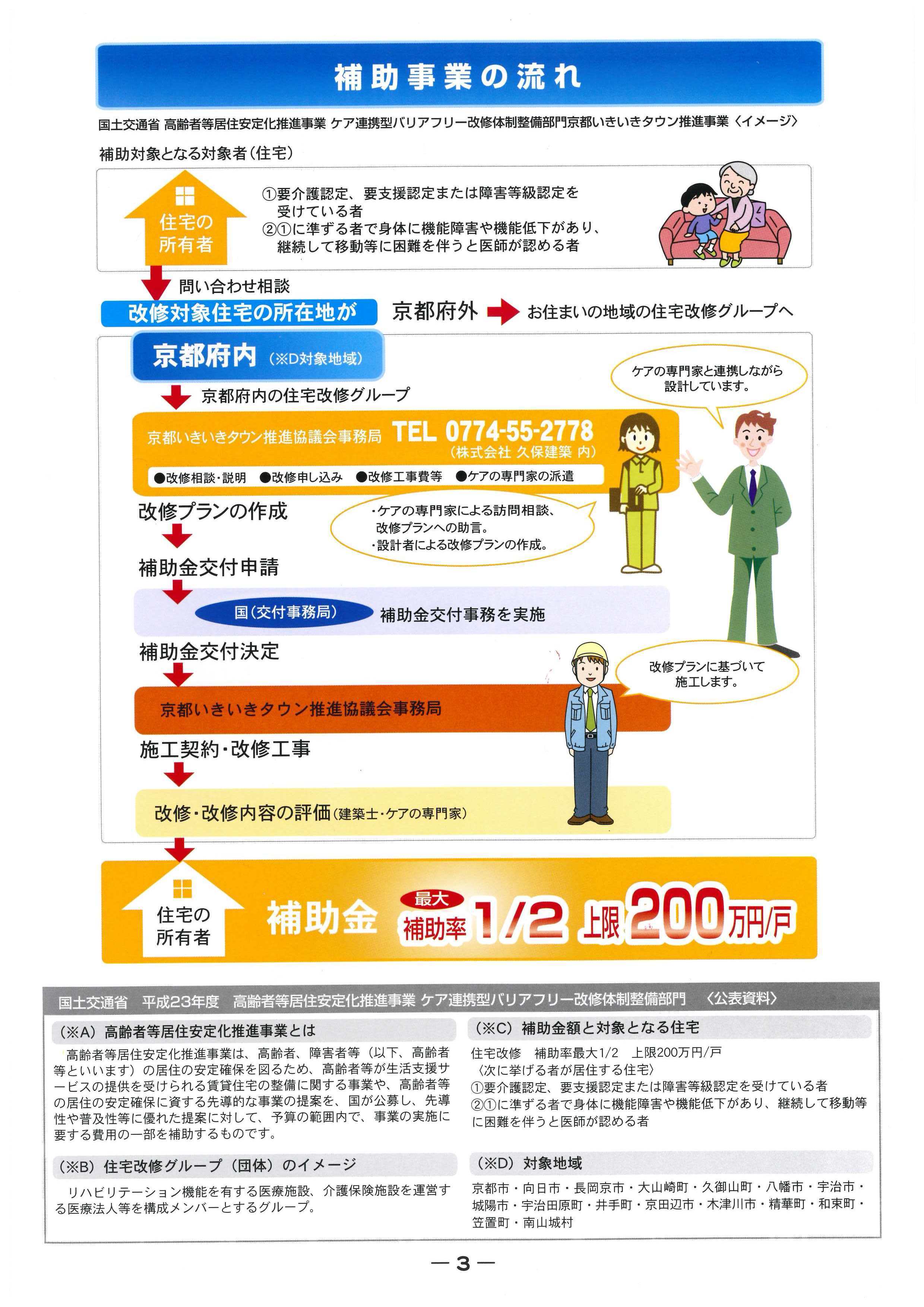ウィズコロナ時代の家づくり
こんにちは。スタッフ西岡です。
私ごとですが、先日コロナ陽性になりしばらく自宅で療養をしていました。
夫と二人暮らしで医療機関の先生にもおそらく家庭内感染するだろうと言われていたのですが、
隔離生活が成功して家庭内感染を防ぐことができました。
そこで、コロナ感染を体験して、この間取りや設備が役に立った!という点をご紹介。
①いざというとき寝室を分けられるように別の個室を作っておいた。
②トイレを1階と2階の2か所つくっておいたので使い分けができた。
③寝室のベランダにシンクを設けていたので歯磨きも別々で行えた。
予備の個室があったのが大きいのですが、個室までは無理でも、寝る場所を隔離できるような畳コーナーなどがあるだけでも安心ですね。
2人暮らしでトイレを2か所つくるのは贅沢でもあったのですが、各階にあるとやっぱり便利です。
飛沫を気にせず歯磨きができるベランダのシンクも大活躍でした。こちらもメインの洗面所と別にサブの手洗いスペースがあると安心です。
さらに、そよかぜの家の特徴である換気システムも大きな安心感をもたらしてくれました。
もちろん窓を大きく開けての換気もしましたが、
寝室にも外からの給気口と汚れた空気を外に出す排気口が設置されていて、しっかりと計画換気されていたことが心強かったです。


玄関入ってすぐの手洗いスペースはもはや定番になりつつあるように、新たに住まいを建てる際に、今後はウイルス感染を予防できる間取りの導入も考える必要がある時代になりましたね。