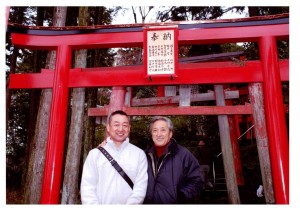昨日の台風の続報です。
昨年来、増築現場での雨漏りについて完了報告ができないままでしたが、今度の大雨で盛らないことを確認してから最後の仕舞をしましょうということになっていました。
昨日の午後、確認に伺うと大丈夫でした。ということで、やっと完了ということになります。長い間ご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。
一方、実は、近所のお寺の庫裏でも雨漏りの周囲依頼を受け、先月屋根瓦の修理をしました。
ここは、20年以上前に古い庫裏を増築した際に、かなり難しい形で納めてある上、10年ほど前に古い方の部分の屋根を葺き替えてありました。新旧の取り合いは大きな谷をつくって納めていますが、そこに古い建物の下り棟が下りてきて、それが新しい建物のケラバに突き当たります。読むだけでも複雑さがお分かりかと思いますが、なんせ筆舌に尽くせない(?!)複雑な納まりなのです。

まずは、谷に穴などがないかを確認しました。相当ゴミがたまっていたので掃除をしましたが、穴は開いていないようです。
ということは、ブラックボックスのような下り棟とケラバの取り合いを見なければなりません。さっそく屋根屋さんに来てもらい、瓦をめくってみました。すると、ちょうど隅とケラバの交差する部分の土が水に洗われたような形跡がありました。瓦の上からはまたくみえない部分です。風が巻いたときに入ってきたのでしょう。そこで、日を改めてこの部分に水切りを入れ、しっくいで固めて瓦を据えてもらいました。これで当分の間はもつでしょうが、十数年もすればまた漏るかもしれません。
とりあえず、こちらも今度の大雨を待って、そのあと天井板の張り替えなどをすることにしましていました。
昨日の午後訪ねてみると、こちらも大丈夫でした。
ついでにもう一つ。こちらは雨漏りはしていませんが、昨年春に引き渡したお宅が少し心配でした。
琵琶湖のほとりに建つ家で、普段でも10mくらいの風が吹くことがありますから、相当な強風が吹いたのではないかと危惧していました。しかも、こちらお宅は、建築家を目指す息子さんが出してこられた概略デザインをもとに設計しており、軒とケラバを大きく出しています。しかも屋根の厚みを薄く抑えるためにいろいろと苦労をしたところです。雪も降る所なので、強度には十分配慮したのですが、風の力は想定を超えることがあります。
こちらはお電話で確認したところ、問題なかったとのこと。
すべてのお客様に一人一人たずねることはできませんが、皆さんのおうちは大丈夫でしたか?
雨漏りや修理のご相談もお受けしていますので、お気軽にお電話ください。