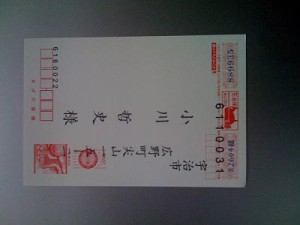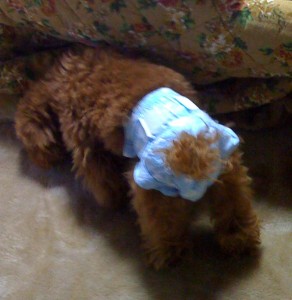健康・自然・家づくり「そよかぜの家ダイアリー」
階段の手すり
 先日完了検査を受けた時に、検査官から階段手すりの取り付けを要求されました。
先日完了検査を受けた時に、検査官から階段手すりの取り付けを要求されました。
これを受けて、写真のように握れる手すりを連続して付けました。
手摺については、行政によって判断がまちまちです。
最近ではリビングに階段を設けいることが多いこともあって、階段そのものをデザインとして見せることもしばしばです。雑誌等で紹介されている階段でも、手摺がわりにロープが渡してあったり、中には完全に何もないものまであります。
今回の現場はご覧の通り手摺壁が付いていて転落防止にはなっているのですが、バリアフリーの考えによるところの、つかむものがないとの解釈でした。事前のお客様との打ち合わせの中では、お年寄りが来られた時は握る手すりがあった方が安心ですねというご説明もしていましたが、邪魔になるので当面はいらないとのことでしたが、検査済証をもらうために、早々に取付をしました。
以前は、転落防止をやかましく言われ、たとえば手摺に格子を用いた場合、格子のピッチに気をつけたりしたものですが、前述のようにそのことは全くとがめられません。おそらく、検査員のチェックリストの項目に載っていないのだと思います。
法律でこう定めてあるからこうしましょうではなく、住み人の立場に立ってデザインは決定しなければならないと思います。運用レベルで、ある程度の融通が利くのはとても良いことだと思うのですが、反面、設計者としては悩むところも増えてしまいます。
家庭用燃料電池、価格発表
先日ご紹介した家庭用燃料電池の販売がいよいよ本格化します。
大阪ガスでは3,255,000円で6月から世界に先駆けて販売を開始します。
国からの補助金が最大で140万円になる見込みで、実質負担額は200万円ほどになると思われます。
このシステムを導入すると、年間1.3トンのCO2が削減できるというのですが、消費者にとって気になる光熱費は、わずかに年間5万円ほど安くなるだけだそうです。
200万円かけて5万円ですから、償却に40年かかってしまうじゃないですか!!
ちょっと現実離れしていますね。ただ、東京ガスでは、2015年には1台100万円にすることを目指すと表明しており、そうなれば20年で償却できますね。でも、償却が終わるまで機械がもつのかどうかは定かではありません。
もうちょっと行政のバックアップがあってもいいんじゃないでしょうか。
塗壁の割れ
自然素材の塗壁はどうしても割れることがあります。多くの材料は割れないように樹脂でかためられていますが、当社で使う材料は、割れてもいいから体にやさしいものというスタンスで選んでいます。とはいえ、割れない方がいいのですが。
尖山ショールームは、高千穂の薩摩中霧島壁を多く使っています。この材料は、火山灰を骨材にしており、乾燥による収縮がほとんどないため割れにくいと言われています。石膏ボードの下地をしっかりと作ればほとんど割れることはありません。
 当社では、尖山で初めて採用したのですが、当時開口部の補強や下地補強の必要な部位にはラワンベニヤを使用していました。実はこれがくせ者で、ベニヤの伸縮が意外と大きいのです。耐火ボードで下地を作ったところはほとんど割れがないのですが、補強にベニヤを入れているところは、ほぼすべて割れが出てきました。竣工後すぐに割れが出てきましたので、原因が下地にありと判断し、それ以後の現場では、下地表面には合板が出ないように施工しており、お客様のお宅では大きな割れが起こってはいません。
当社では、尖山で初めて採用したのですが、当時開口部の補強や下地補強の必要な部位にはラワンベニヤを使用していました。実はこれがくせ者で、ベニヤの伸縮が意外と大きいのです。耐火ボードで下地を作ったところはほとんど割れがないのですが、補強にベニヤを入れているところは、ほぼすべて割れが出てきました。竣工後すぐに割れが出てきましたので、原因が下地にありと判断し、それ以後の現場では、下地表面には合板が出ないように施工しており、お客様のお宅では大きな割れが起こってはいません。
4月で丸5年を迎えますが、構造材のあばれによると思われるものも出てきました。
写真はおそらく柱の背割れの開きと梁のねじれの影響だと思われます。この部分は耐火ボードの下地だったはずですが、去年の暮にクラックに気付きました。
大きな壁面に塗壁材を使用する際は、ある程度の割れは許容しなければいけないということを、お客様にご理解いただかなければ使えません。
薪ストーブが大活躍!!でも湿度は大丈夫?
急に寒くなりました。
今朝の宇治市の最低気温はマイナス2℃でした!!
こんな時こそ薪ストーブが大活躍です。
またちょうどいい具合に、現場の残材(杉・松など)が少しあったので、これを燃料として活用してみました。
針葉樹は油分を多く含んでいるので、高温で燃やさないとクレオソートが煙突などに付着してしまいます。かといってあまり高温にするとストーブ本体を傷めてしまうので注意が必要です。
私がつかっている薪ストーブは、ヨツールのF500です。このストーブは針葉樹も燃やすことができます。
針葉樹は細いものばかりということもあって、あっという間に燃えてしまうので、1時間ほどで燃料を補給してやらなくてはなりません。結構面倒ですが、一日分が燃料代タダの上に倉庫の整理もできたので、そのくらいの手間は仕方ないかと納得です。
こんな調子で燃やし続けていると、室内は暑いくらいになってしまい、夜にはストーブを消さなくてはならないほどでした。
そこで、寝るときにはいつもの温水ラジエータのスイッチを入れておきました。
おかげで、マイナス2℃の屋外にもかかわらず、朝の室内は20℃でした。
ところが、湿度がえらいことになってました。
寝る前に、2台の加湿器の水を満杯にしておいたのですが、ちょっと朝寝坊して7時に起きたときにはすでにからっぽ。
湿度は何と35%でした。
 さっそく加湿器に水を入れ、10時現在ようやく40%ほどに回復しました。
さっそく加湿器に水を入れ、10時現在ようやく40%ほどに回復しました。
ちなみに、現在外は気温4℃、湿度50%ほどです。このときの水蒸気量は、3.2g/m3です。
この外気が換気によって室内に入ったとき、20℃に温められますから、そのままだと湿度18.5%になります。(計算方法は今日は省略します)
湿度を40%に保つためには、5.4g/m3の水蒸気を供給しなければなりません。
換気量は、法定換気量の1時間当たり0.5回、我が家の容積を600m3(200㎡×3m)とすると、一時間に入れ替わる空気の量は300m3です。
ということは、1時間当たり、5.4×300=1620gの水蒸気が必要ということになります。
すなわち、24時間当たり、38.4リットルもの水がいるということなのです!!!②リットルのペットボトルが19本ですよ!!!ましてや、下がってしまった湿度を上げるためには、さらに多くの水がいるということになります。
我が家の加湿器は、8リットルと4リットルの2台です。これがフル回転すれば、どうにか供給できる量です。「うちの壁は調湿性能があるから乾燥しませんよ」なんていう業者さんがいますが、冬の間毎日こんな日が続いたら、魔法でも使わない限り無理なんですよ。
完成現場。今なら見学も可能です!
今朝、JIOの検査が終わり、午後は宇治市の検査を受けて完了です。
フローリング・階段・窓枠・建具は杉材でコーディネート。壁は健康塗壁ダイヤトーマス。
自然素材でナチュラルテイストな仕上げですが、キッチンにビビッドなカラーを入れました。
来週にはお引っ越しなので、それまでに内部は、床のオイル塗り・カーテンの取付・各器具の試運転調整、外部は門柱やウッドデッキなど、大忙しです。
そんなわけで、工事をしながらになりますが、週末から来週水曜日まで、見学していただくことも可能です。
場所は宇治市広野町、広野中学のすぐ近くです。ご連絡いただければ詳しい場所はお知らせします。
工事の予定との調整がありますので、必ず事前にご予約をお願いします。
ご予約は
電話 0774-86-4962
湿度を上げると暖かいんだぁ~
 私の事務所が厳寒であることは先日書きましたが、おかげでのどの痛みがなかなか治りません。
私の事務所が厳寒であることは先日書きましたが、おかげでのどの痛みがなかなか治りません。
何とかしないとと思い、昨日は加湿器を持ちこみました。
暖房もエアコンに加えて、デロンギヒーターを持ちこみました。
1時間ほどで、エアコンはアイドリングに入りました。(デロンギの力は結構すごい)その後エアコンを切った状態で、デロンギと加湿器の運転を続けました。すると、昼過ぎには、気温19℃湿度55%という快適な環境になりました。
相変わらず、足もとは寒いものの、湿度を上げることで、体感的には格段に温かく感じます。
ちなみに、加湿していない状態だと、20℃まで温度を上げると、湿度は30%を切ってしまいます。
夏の暑さを説明するときに、「水蒸気は熱をためているようなものだから、除湿すれば体感温度は下がりますよ」という説明をよくするのですが、冬のこの時期に、水蒸気の持つ熱を思いっきり体感しました。
太陽光発電システム設置の助成金申請を受付中
太陽光発電システムの設置に対する助成金の制度が復活しました。1月13日から受け付けが始まっています。
以前、財団法人新エネルギー財団が行っていた流れとほぼ同じですが、今年からは、太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)というのが組織され、これが窓口となるのだそうです。京都府では、そのまた窓口として、特定非営利法人地球温暖化防止府民会議に申請をします。
助成金額は1KWあたり7万円で、工事費の10%以内で10KWが上限ということなので、最大で70万円もらえるということになりますが、通常の住宅ですと、3~4KWの場合がほとんどですので、250~300万円くらいの工事費に対して、21~28万円もらえるということになります。
これと併せて、各地方自治体の助成制度を併用できます。東京都では30万円ももらえますが、近隣では、京都市と精華町が行っていますが、今年度の対応はまだわかりません。例年通りですと20万円程度ですし、他の市町村も行うかもしれません。
ところで、太陽光発電システムの発電量はどのくらいなのでしょうか。
ものすごくおおざっぱに言って、住宅の場合年間8~10万円程度電気代が安くなります。それに対して、初期投資が助成金をもらっても200万円以上ですから、元をとるのに20~30年かかるということになります。また、5月から電気料金が大幅に下がるという話もあり、そうなると償却年数は延びてしまいます。
一方、今まで太陽光パネルの変換効率を上げることばかりに注力してきたメーカー各社が、低価格化のために量産を始めており、値段はぐっと安くなるものと思われます。
とはいえ、まだまだ「お得です」とは言い難い状態ですが、てっとり早くCO2削減できるので、行政のさらなる支援に期待しましょう。
J-PECへの申請は3月末が締め切りですので、設置を考えようかという方はお早めにご相談ください。
健康塗壁ダイヤトーマス施工中
宇治市の現場で健康塗壁ダイヤトーマスを塗っています。
目地処理をしたボードの上に一発仕上げで施工します。職人さんのセンスで柄が決まってしまいますので、実際に現場で塗パターンを試しながら進めていきます。
この材料は、ペーストの状態で入荷しますので、色の調整と攪拌をするだけでそのまま塗れます。ほぼ中性なので手あれもなく、1~2mmの薄塗りで軽いので、女性でもぬれるほどです。
実際、当社でも左官屋さんに塗ってもらうこともありまあますが、必ずしもそうではありません。左官職人さんは、ピシッと塗ることを毎日しているので、ラフな仕上げをするのがどうも性に合わない感じなので・・・
写真の職人さんは本職はタイルやさんです。下地処理はクロス屋さんがして、塗りつけを手伝ってもらいました。普段タイル用の接着材の塗りつけをしますので、コテをうまく使って均等な厚さに塗りつけるのは左官屋さんバリです。あとは、センスに任せてパターン付します。
この材料、施工中でも全く臭いがありません。ドイツ製のエコバインダー(のり)を使っているのだそうですが、これでどんな下地にでもついてくれるのですから不思議です。また、主成分のケルザイムは食品や化粧品にも配合されるほど安全なものです。
健康塗り壁というだけのことはあります。
当社は、シラスの中霧島壁とダイヤトーマスを使い分けています。
中霧島壁は、施工が結構難しいので、左官職人の腕が必要です。塗厚が結構あるので、その分吸放湿性能は高く、テクスチュアもボリューム豊かです。デザイン的にきちっとした仕上げの時に使います。
今回はラフな仕上げをイメージしているので、ダイヤトーマスを選択しました。
完成写真はそのうちにアップしますのでお楽しみに。
外張り断熱の力を温度で比較
このところ寒い日が続いています。そんな時に限って事務所でのとりまとめ作業があって、ほぼ一日中事務所で過ごすことになってしまいました。普通事務所だと暖かくていいのかとお思いでしょうが、私の事務所は実家の一部屋を改造して作ったものなので、いわば田舎の大きな一軒家の一角です。
田舎の大きな家というと、とにかく寒いのです。ここで暮らしている私の母は、普段過ごしているLDKに大きな石油ストーブを置いて、朝一番にスイッチを入れます。それに何よりコタツがありますから、寒い中でも暖を取って過ごすことができます。
ところが、事務所にはもちろんコタツもありませんし、20年ほど前に取り付けたエアコンがあるだけです。あまりの寒さに、足もとにパネルヒーターを置いて、そこに足をのせて仕事をしています。もちろんジャンパーを脱ぐことはできません。
一方、私が住んでいる自宅はというと、5年前にそよかぜの家仕様で建築しています。だいたい20℃くらいをめどに暖房をしているのですが、21℃の事務所とは比較にならない暖かさです。暖房器具は、温水式のラジエーターが2台、ダイニングとキッチン部のみ床暖房が入っています。エアコンは冬場は使ったことがありません。輻射暖房ですから音もなく快適です。
まずは事務所、昨日の午後2時ごろ、エアコンの設定温度は21℃、運転が停止している状態です。このとき、エアコンのリモコンの高さに温度計を置くと、確かに21℃になっているのですが、床に置くとなんと15℃しかありません。立ち上がった時の頭の高さ(1.8m付近)は25℃もありました。運転を始めて6時間以上たつのに、足もとと頭とでは10℃も温度差があったのです。
一方自宅で今朝はかってみると、床に置いた温度計は19.5℃吹抜けの天井近くにおくとさすがに21℃、私自身が一番寒いと感じる暖房を何もしていない寝室の床付近でさえ、なんと19.5℃。家中の温度差がわずかに1.5℃しかありません。
上が一番高かった吹抜けの天井近く、下が寝室の床です。
防犯のための照明
年末にライトアップが各地で行われたのを受けて、癒しの照明についてコメントをしていました。キラキラと輝く電飾よりも、やわらかな電球色の光の方が日本の風景を美しく見せてくれるという考えが広まっています。色とりどりの電飾で飾られたライトアップもいいですが、嵐山の花燈篭のような落ち着きのある”あかり”が、日本の風景にはマッチするという考えが増えてきました。
先日ご紹介した景観配慮型の京都のコンビニも、外から見える照明を電球色を使用しています。
照明を青色にすると、犯罪が減るというものです。実際にJR西日本は、踏み切りの照明を青色にしているところがあり、飛び込み自殺の抑止につながったとしています。奈良県警も街灯を青色に変更することで犯罪が減らす効果があったとしています。
写真は宇治の天ケ瀬ダム。残念なことに自殺の名所でもあります。ここも昨年末に照明が取り替えられ、ごらんのように青色になったそうです。風景としては寒々しい感じなのですが、心理的には鎮静効果が高いのだそうです。
玄関は脳を安定させる
知って得する!ブリーズ・カンパニーの「建築医学」___karte1
”玄関は脳を安定させる”
正月早々ショッキングなタイトルですが、ブリーズ・カンパニーの2009年カレンダー「建築医学」の1月のコラムタイトルです。
以下転載
玄関は人の顔や脳にあたります。玄関が汚れていたり散らかった家で暮らしていると、脳が委縮する傾向があります。逆に、整理整頓・清潔を徹底し、広々とした印象にすることで、ストレスが緩和され安定した精神状態を保てます。狭い玄関には鏡を置くなどの工夫で、玄関に入った瞬間に「ホッ」とくつろげるような空間にしましょう。
こんな建築医学カレンダーが予備にとっておいたものが少しだけ残っています。
ご希望の方はメールにてお申し込みください。
七草粥
先程、お昼に七草粥を食べました。
正月の間に食べ過ぎ飲み過ぎで疲れた胃腸を助けてくれるのだとか・・・。
いわゆる春の七草が入っているのですが、最近では七草粥セットになって売っているそうです。特に癖もなく普通においしく食べられました。
ところで、春の七草ってどんなんやったっけ??というわけで調べてみました。
せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろなのだそうですが、何のことかわかりません。
すずな・すずしろはそれぞれ、かぶ・大根、せりはそのまませりですが、そのほかはいわゆる雑草のようです。けれども、枕草子の時代から正月7日に食べられていたというのですから、超ロングセラーメニューといったところです。
ちなみに、秋の七草は食べません。
日本郵便の力
正月早々珍しいものが届きました。
これでもちゃんと届けてくれる日本郵便はすごい!!
それにしても、投函された方は気づいていないのか??今度お会いした時にお話しします。
そういえば、最近年賀状のあて名書きを手書きで書かれる方はほとんどなくなりました。私の所に届いたものを数えてみても、1割もありませんでした。かくいう私もパソコンで宛名刷りしていますが、刷り終わってから宛名を確かめて、一言コメントを添えるようにしています。この方はずいぶん急いでおられたのでしょう。
ところで、この年賀状、普段通信のない遠方の友人などとの連絡は楽しみなものですが、ドカンとまとめて届くのでなかなかゆっくり読めませんし、誰からのコメントだったのかごちゃごちゃになってしまいそうです。また、喪中の方に出してしまったりということもありがちです。そんなことを考えてか、年末に挨拶状が何通か届きました。キリスト教の国ではクリスマスカードなのでしょうが、それもなじまないので、一年間のお礼と来年もよろしくという挨拶状という感じです。ドカンとくる年賀状に比べれば印象に残ります。喪中も気にしなくて済みますし、これから増えるかも知れません。そもそも、三ヶ日くらいは家でゆっくりしてというスタイルが全くなくなり、元旦からバーゲンに出かけるような時代ですから、年賀状のあり方も変わらざるを得ないでしょう。
私自身は、プライベートの年賀状は年末ぎりぎりに投函しましたが、会社としては今回出せませんでした。年賀状に代えて、早々のうちにニュースレター出すつもりです。松の内が過ぎたころに、ゆっくり読んでもらいたいと考えています。
新年のごあいさつ
新年明けましておめでとうございます。
昨年末に新しいページに移行し、新しい方にも見ていただけるようになり、ブログを書くのも力が入っていきました。今年はもっと面白おかしい内容を書いていくつもりですので、よろしくお願いいたします。
今日は、お正月気分で着物姿をアップしました。老け顔がより一層おっさん臭くなってしまいました。
私の実家のあたりでは、元旦にお寺と神社に年始のあいさつに行くのですが、去年から着物で行っています。(一張羅ですから毎年同じものですけど)着物を着て下駄を鳴らして歩いていると、何となく自分も日本男児だみたいな感じで、少し強くなったような気になります。けれども着なれない上に下駄では車も運転しにくいので、そそくさと着替えてしまいました。
氏神さんにお参りした後、家族で初詣に出かけました。
今年は、自宅の近くにある世界遺産、宇治上神社に行ってきました。
ここは、神社としては日本最古と言われ、本殿は平安時代に建立されたものだそうです。さすがに、元旦は大勢の参拝客で混雑していたので、建物をじっくり見る余裕もありませんでしたが、ひと通り見ても、それらしい古い建物は見当たりませんでした。
それもそのはず、写真の本殿は覆屋で、中に本殿が三つ並んでいるのだそうです。正月から調査不足でミスってしまいましたが、今度行った時にじっくり見てきます。
ともあれ、家族の健康と事業の発展を祈願して帰りました。
新年早々、ニュースではイスラエルの空爆やアメリカの崩壊が伝えられています。100年に一度どころではなく、人類が経験したことがないような激動の時代を迎えているのかもしれないと心配になりますが、何の不安もなく無邪気に遊んでいる子供たちを見ていると、「悩んでもしゃぁ~ないな」とも思えてきます。
自分自身と仲間を信じ、軸をぶらさず、頑張っていきたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
高断熱住宅に住み替えると医療費が減る!?
「安全な住環境に関する研究会」によると、08年、断熱性能の高い住宅に住み替えた101世帯343人を対象に、住み替え後の健康状態をヒアリングした結果、手足の冷えが解消する、せき、のどの痛み、喘息が改善するなど、体調の向上や病気発症の抑制が確認されたとのこと。
ただ、アレルギー性鼻炎などが住み替えを機に増加した症例もあり、もろ手をあげてということではなさそうです。やはりそこは「本物の健康住宅」でないといけません。
近畿地方の家の中の気温は日本中で一番寒いということを聞いたことがありますが、寒さをがまんすることで体調を崩すよりも、快適な空間で健康に暮らす方が、医療費が抑えられてお得ということです。
従来光熱費が安くなる分でイニシャルコストは取り返せますよというお話をしていましたが、医療費の分を計算すると、お得ということになりそうです。なにより、快適な毎日はお金で評価できませんけどね。
家庭用燃料電池が世界で初めて市販されるらしい
時々話題に上げていた、現在最も環境にやさしいとされている家庭用燃料電池システムが、いよいよ普及レベルになりそうです。
今年になって、東京電力や新日本石油がモニターを募集し、実証実験を行ってきたのですが、耐久性やコストの面でめどが立ったようです。折しも、一般のニュースでは電力価格の大幅値下げが報じられていますが、オール電化一辺倒に歯止めがかかりそうです。
写真は、新日本石油が現在使用しているもので、LPガス用と灯油用があります。市販レベルになると、都市ガス用がライナップに加わると思われます。
エネファームと名付けられたこのシステムは、燃料に含まれる水素と空気中の酸素とを化学反応させることで発電するので、窒素酸化物や硫黄酸化物の発生がほとんどない上、使用する場所で必要なだけ発電するので、余熱でお湯を沸かすこともでき、送電ロスもありませんので、トータルで高いエネルギー効率を達成するというものです。
夜は料金の安い電力会社の深夜電力を使い、昼間は自家発電を利用することで、ランニングコストはずいぶんと安くなるものと思われます。
あとは、コストの問題で、今までイニシャルコストが300万円くらいといわれていましたが、市販となるとどれくらいの価格になるのか注目するところです。特に、LPガスのエリアでは、オール電化切り替えに対抗する切り札みたいなものですから、イニシャルを抑えたリース方式などを出してくるんじゃないかと期待してます。
ただ、現在普及しているガスの発電システム(エコウィル)をみても、発電量が8KW/1日・1KW/1時間までに制約されており、これではメリットが半減します。電力会社との折衝でそのへんが緩くなるといいのですが・・・
クリスマス
今日はクリスマスです。クリスマスがキリストの誕生日だということはどれくらいの人が知っているのだろうか?
23日に子供が通う中学でクリスマス行事が行われ、キリスト生誕の演劇を見ました。この学校の生徒たちは少なくとも知っているでしょうが、ミッションスクールでない限り、学校で教えることはないでしょう。
ともあれ、2000年前に現れた救世主が、現代社会にも必要かもしれません。
 クリスマスとは関係ありませんが、「新型エスカレーター」ができたというのでご紹介します。
クリスマスとは関係ありませんが、「新型エスカレーター」ができたというのでご紹介します。
新型というからどんな形なのかとお思ったら、ご覧のように変わったのはベルトだけです。
ベルトに黄色い丸がプリントされていて、遠目に見ても、上りなのか下りなのかがはっきり見えるというものなのです。
「そんなんなくてもわかるやろー」という声が聞こえてきそうですが、これだけで事故防止につながるのだそうです。
そのうちに駅や商業施設で増えるかもしれません。