2023カレンダー配布中

毎年恒例のオリジナルカレンダーを配布中です
今回のテーマは建築用語豆知識
前にも似たようなテーマがあったかもしれませんが、今回は京町屋や古民家で使う言葉を選んでいますので、ぜひご一読ください
カレンダーが欲しいという方は、若干予備がございますのでお声がけください
mailto:breeze@soyokazenoie.com
今年も残すところ一週間となりました
おかげさまでたくさんの方とお仕事をさせていただき、心より感謝申し上げます


毎年恒例のオリジナルカレンダーを配布中です
今回のテーマは建築用語豆知識
前にも似たようなテーマがあったかもしれませんが、今回は京町屋や古民家で使う言葉を選んでいますので、ぜひご一読ください
カレンダーが欲しいという方は、若干予備がございますのでお声がけください
mailto:breeze@soyokazenoie.com
今年も残すところ一週間となりました
おかげさまでたくさんの方とお仕事をさせていただき、心より感謝申し上げます





5月から工事を進めておりました、宇治平等院表参道の中村藤吉本店平等院店が、いよいよ本日オープンです
今回のリニューアルで、セルフ形式になり、テイクアウトして川沿いテラスや芝生庭のベンチで楽しむこともできます
店内も大きく模様替えをし、くつろげる空間となりました
今まで使っていなかった2階も開放されます
宇治川の眺めは壮観です
ぜひご利用ください
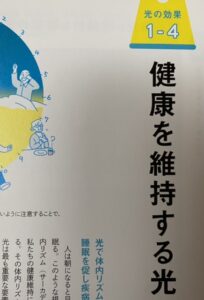
とても興味深い
部屋の明るさ、光の色目、照らし方、などなど、生活の中のシーンによって使い分けることで、健康を維持することにつながるという研究が進んでいるとか
健康住宅としては取り入れたい

久しぶりに施工事例を更新しました
1年分くらいを一気にアップしましたのでどうぞご覧ください
https://www.soyokazenoie.com/portfolio/

耳付の栗ムク材の中央部分に、“なぐり”加工を施してもらいました
ちょうな(ちょんな)ではつって模様をつける手法で、はつった面がそのまま仕上げとなる一発勝負の加工です
材料も加工も、同じものは二度とできません

久御山町で完成した現場をご覧いただいております
おかげさまで予約は満杯となりました
来週は伏見で開催します。
こちらは若干の空きがあります
ご希望の方は今すぐお問い合わせください
当社の施工事例が取り上げられました
そよかぜの家はZEHにも対応しています
先日のニュースで、水漏れ修理で法外な請求をする業者が逮捕されたと、大きく報道されました。
ネット検索で上位に出てきてるとか、口コミが良かったとかで依頼して、被害にあわれた方が多かったようです。
このところ家一軒丸ごとというくらいの大掛かりなリフォームのご相談が多くあります。
大手不動産会社やハウスメーカー系列の会社が営業攻勢をかけているのかもしれませんが、お客様から相談を受けるとき、すでにその提案を持っておられる場合もあります。
その提案がちょっと???なことが非常に多いです。
四方に下屋をめぐらしたような和風の家を建てたことがないのでしょうね、組み方がわかっていないから、大事な壁をどんどん撤去して、外してもよい柱を大事そうに残して、いかにも構造に配慮しているような・・・
リフォームって簡単に考えがちですが、新築よりもずっと難しく、幅広い知識が必要です。
大手だから安心と思ってはいけません。昨日採用された人が図面を書いて、工事が終わるころには辞めているかもしれません。
やっぱりそこは、信頼できる専門家に相談しましょう。
一方で、建築士って専門家なのに扱いが悪すぎると思います。
体調が悪くなってお医者さんに診てもらったら、診察料を払いますが、家の具合を見てもらっても無料なのが常識になっています。
言ってみれば往診して治療方法の提案をしているのに、診察料を請求できないのです。
先のニュースでは、きちんと相見積もりをとって発注しましょうというしめくくりでしたが、見積するには相当の労力が必要なのですから・・・
相見積もりをとるのが正しいのではなく、信頼できるかかりつけ医のような存在が必要なのだと私は言いたい。



右京区の現場で気密測定に立ち会いました。
普段は樹脂サッシを採用することが多いのですが、お客様が山間で風が強いと心配しておられたので、耐風性能を重視した窓を採用しました。
断熱性能はデータで確認できますが、気密性能は現地での確認が必要です。
測定結果は
c値0.3 cm2/m2
と、なかなか優秀な数字で、気密性能も高いことが確認できました。

コロナが猛威を振るっているなか、改めて健康住宅が注目されています。
ZEH(ゼロエネルギー住宅)の性能を持ちながら、自然素材に包まれた気持ちの良い家をご紹介しています。
ぜひご覧ください。
https://www.soyokazenoie.com/portfolio/6617/

宇治で人気のカフェ、中村藤吉本店。
コロナ対応のため客席を拡大し、ソーシャルディスタンスを確保されました。
いつもは大行列で、なかなか入店できないのですが、さすがに緊急事態宣言の元ではほとんど混雑はありません。今なら並ばずには入れるので、チャンスかもしれません。
内装はもともと工場であった建物の雰囲気を再現するため、あえて荒壁を残したり、小屋裏の煤けた部分を見せたりと、なかなか味わいのあるものになっています。
奥の窓の向こうには茶畑をイメージしたこて絵がつくられました。

左官屋さんがこてを使って何回も塗り重ね、立体的な絵になりました。これだけでも一見の価値はあります。
外壁仕上げとして人気のシラスそとん壁ですが、窓周りなど水垂れで汚れることがあります。

写真は尖山ショールームの東面窓まわりです
築17年、結構な汚れです。当初、メーカーの高千穂さんは、高圧洗浄で洗って落とすことを薦めていましたが、新しい洗浄方法を教えてくれたので、実験してみました。

ご覧の通り、若干解析は残るものの、かなりきれいになりました。
薬剤散布後30分ほど放置しますが、それも含めて作業時間は45分ほどでした。
コロナ禍で観光客のいない嵐山で、大雨に備えるための可動壁が付けられました。
それに付帯して、堤防沿いに小さな建物を建設。
景観を損なわないように、目立たないことが重要なんでね。

近くにある機材置き場は、木柵で修景

2021年、株式会社ブリーズ・カンパニーは設立15年を迎えます
昨年5月にスタッフを加え、新たなステージに向かって歩み始めておりますが、今後も変わらず、お客様と職人さんたち、それをつなぐ私たちの三者が、末永く幸せでいられるような家づくりを続けていきたいと考えています。
コロナ禍の続く中、住まいにおいても変革が求められ、当社の掲げる”きれいな空気の中で暮らす”ことが注目されています。
暮らす人の健康を重視するスタンスを再確認し、試行錯誤を重ねながらも、地域の皆様のお役にたてるよう研鑽を重ねたいと思います。
変わらぬご指導ご鞭撻をお願い申し上げます
令和3年1月4日
株式会社ブリーズ・カンパニー
代表取締役 小川 哲史

地元のお稲荷さんの参道鳥居
1年おきに役員さんの交代にあわせて寄付を集めて建てておられます。
今回は昭和63年に建てられたものを取り壊して建てました。
いったいいつから続いているのかわかりませんが、私が初めてお手伝いさせていただいたのが平成18年。これで8基目となりました。
あやかって私も商売繁盛!!
松の内も過ぎましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今年はどうしたことか、各現場とも工程がタイトで、正月気分を味わうことなく過ごしてしまいました。
そんなスケジュールの中進めております現場が、2月後半に完成を迎えます。完成時には、久しぶりに内覧会を開く予定ですのでご期待ください。
大阪府茨木市と京都市左京区で、ほぼ同時進行で進んでいます。
いずれもこれまで施工してきたものより、断熱性を少し高めて、いわゆるZEH(ゼッチ)基準の性能を持たせています。
工事中の見学を希望される方は、メール等でお知らせください。
本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
日経ホームビルダーに、大きく特集が組まれていました。
断熱材の内部で結露が起こる可能性があることがわかっているのに、室内側に防湿シートを張ることで対処できるという考えが間違っています。フラット35の仕様書でも、断熱材メーカーの仕様書でも、夏の対策はされていません。
記事では雨水の進入が原因との見方をしていますが、そうではありません。やってはいけないことをやらせているんですから、結露して当たり前です。
言わんこっちゃない!
中学校で習う程度の知識があれば、誰でもわかる結露の理屈。
私が2005年にまとめたものを、2012年に再編しました。非売品です。
なぜ繊維系断熱材を使わないのか、なぜ熱交換型換気扇を使わないのか、それは健康で快適に暮らすためなんです。
そよかぜの家にお住いの方は、夏の結露も心配ありませんので、どうぞご安心ください。